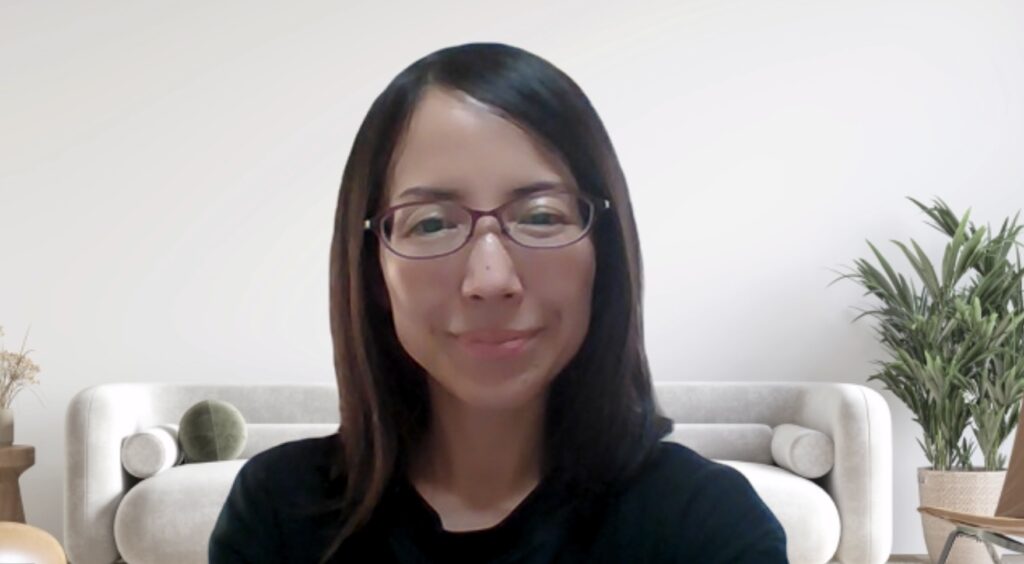みなさんは「アダルトチルドレン」を知っていますか?
なんとなく目や耳にしたことがある、と言う方が多いのではないでしょうか。
しかし、SNSなどが発達したことでその単語だけがひとり歩きし、字のイメージから”アダルトチルドレン=大人になりきれない大人”というように、本来とは違う意味で認識してしまっている人も増えています。
本来の“アダルトチルドレン”とは、機能不全家族、問題を持つ親などによって子どものころに心的外傷を受け、トラウマを抱えたまま大人になった人たちのこと。
医学的な診断名ではありませんが、多くの人が成人してからも生きづらさを抱えて過ごしているのです。
今回の記事では、そんなアダルトチルドレンの種類や原因、克服の仕方などをご紹介します。
アダルトチルドレンの6つのタイプ

アダルトチルドレンは、大きく6つのタイプに分類されています。
ここでは、それぞれの名前とその特徴についてご紹介します。
ACの中で、どのタイプに当てはまるかな?と確認をしてみてください◎
①ヒーロー(英雄)
ヒーローは、勉強や運動、習い事などで、親から良い評価を得られることを最優先します。
側からはしっかり者や頑張り屋、一生懸命で真面目な子と見られがちですが、その努力は「親に叱られたくない」「家族の雰囲気を壊さないようにしなければ」という自己防衛の気持ちからくるもの。
そのため、挫折や失敗をしたときには急に心が折れてしまう傾向にあります。
②スケープゴート(生贄)
スケープゴートは、ヒーローとは正反対のタイプです。
問題行動を起こしたり、極端に悪い成績を取ったりするなど、家族の中での「悪者」の立場を背負うのが特徴です。
家族の怒りや不満をすべてひとりで受け止める「感情のゴミ箱」のような役割を担うことで、家族のバランスを取ろうとするのです。
③ロスト・ワン(いない子)
ロスト・ワンは、「元々いなかった子ども」として、家族団欒に加わらず、存在を消して生きていこうとします。
「いない子」として振る舞うことで、家族から傷つけられないようにしているのです。
アダルトチルドレンの中でも目立った特徴がないため、他のタイプと比べてアダルトチルドレンであることを自覚しにくい傾向があります。
原因はネグレクトや過干渉と言われていて、大人になると「自分は必要とされていない」と孤独を感じることがあります。
④ケアテイカー(世話役)
ケアテイカーはその名のとおり、過剰なまでに献身的に、自分のことを後回しにしてでも家族の世話をしてしまいます。
そうすることで、家族の機能が崩壊しないようにバランスをとっているのです。
また、ケアテイカーとしての役割を全うすることで、自分の存在価値を見出します。
相手から褒めてもらえたり感謝されたりすることを求め、世話自体に依存している場合もあります。
そのため、社会に出た後も過剰な世話をしてしまう場合が多く、それが理由で人間関係のトラブルに発展するケースもあります。ケアテイカーについては、「アダルトチルドレンのケアテイカーを克服するたったひとつのコツ」で紹介をしています。ぜひ、読んでみてください。

⑤ピエロ(道化師・クラウン)
ピエロは、家族の雰囲気が暗くならないように冗談を言ったりおどけたりなど、ひょうきんに振る舞います。
一見明るい性格に見えますが、それはあくまでその役割を演じているに過ぎません。
場合によっては体調が悪いことさえも隠して道化を演じることがあります。
本当は、常に他人の顔色を伺って、険悪な雰囲気にならないように怯えているのです。
⑥イネイブラー(慰め役)
イネイブラーはケアテイカーと少し似ていて、自分を犠牲にして、他者へ過剰なほど献身的に尽くします。
しかしその献身の方法は相手のためにならないことが多く、むしろ問題行動を助長し、状況を悪化させてしまいます。
例えば、アルコール依存症の親のためにお酒を用意するという行為などは、代表的なイネイブリングです。
彼らは、他者に尽くすことで自分自身の問題から目を背ける傾向があります。
アダルトチルドレンが生まれてしまう幼少期の環境

アダルトチルドレンは本人の性格や病気ではなく、幼少期の家庭環境が大きく影響を与えています。
ここでは、どういった環境がアダルトチルドレンを生んでしまうのかを見てみましょう。
機能不全家族のもとで育った
まずは、アダルトチルドレンの定義にも含まれている「機能不全家族」が一つの大きな要因となります。
機能不全家族とは、お互いを尊重することも支え合うこともできず、生活がうまく機能していない家族のこと。
外からは一見普通の家族に見えても、親が子どもに無関心や過干渉などで日常的にストレスを与えていたり、情緒的なコミュニケーションがない家族の場合は、すべて機能不全家族と言えるのです。
親からの虐待を受けていた
また、代表的な原因の一つに、家庭内での虐待があります。
ネグレクト(育児放棄)も虐待のひとつで、子どもに必要な教育を受けさせない教育ネグレクト、子どもから金銭を搾取するなどの経済ネグレクトのほか、家に閉じ込める、食事を与えない、医療を受けさせないなどもネグレクトにあたります。
このような虐待が日常的に行われる環境にいると、虐待から逃れるために自分を抑圧したり、無理していい子を演じてしまうようになるのです。
“毒親”に育てられた
最近SNSなどでよく見かけるようになった”毒親”という言葉。
これも、アダルトチルドレンになってしまう要因の一つです。
毒親とは読んで字の如く、子どもにとって「毒」となる親のこと。
子どもの言動に過剰に口出しする、監視する、強いプレッシャーを与える…などの言動で、子どもの自由や幸せだけでなく、思考力や判断力までも奪っていくのです。
それにより、社会に出た時に周りにうまく適応できず、苦しんでしまうのです。
毒親にも様々な種類がありますが、そのうち2つを例として挙げてみます。
アルコール依存症の親
アルコール依存症の親も”毒親”に分類されます。
アルコール依存症は「お酒を飲むこと」が最優先となってしまうため、お酒がなくなると怒鳴ったり、暴れたりします。
普段は優しく立派な親だったとしても、アルコールが入って人格が変わってしまうことで、子どもの心身へ悪影響を与えるのは言うまでもないでしょう。
子どもを理解しようとしない親
当たり前のことですが、人は一人一人それぞれ違う個性を持っています。
特に子どもは成長の過程にあるため、発達速度なども様々。
物静か、活発などの性格に加え、衝動的な行動をとりやすい、神経過敏などの特性ともしっかり向き合ってあげることが大人の役割です。
ですが、こういった子どもの性格や特性を理解できない・理解しようとしない親がいるのも残念ながら事実。
子育ては自分の思い通りにいかないことがほとんどですが、それに疲れたり腹を立ててしまうことで、子どもを叱り飛ばすだけになる人も中にはいます。
これも立派な”毒親”のひとつです。
もっと詳しくアダルトチルドレンの原因について、「アダルトチルドレンとは?特徴や生活における影響と脱却方法について解説」でも紹介をしています。ぜひ、読んでみてください。

アダルトチルドレンは克服できる

冒頭で述べたように、アダルトチルドレンは病気ではありません。
そのため、自分と向き合って、自分を認めてあげることで、克服していくことができます。
ここでは、具体的にどのような方法で克服していけるのか、ご紹介していきます。
アダルトチルドレンに関する知識を勉強する
アダルトチルドレンかもしれないと自覚したら、まずはアダルトチルドレンについて調べてみましょう。
これまでに書いてきたことはほんの一部分です。
どういった症状なのか、原因は何かなど、自分なりに調べて理解を深めてみてください。
知識を獲得することで、自分が今どういう状況なのか、これからどうしたら良いかなどを見つけやすくなるはずです。
カウンセラーや専門家に相談する
メンタルクリニックなど、専門機関を活用してみるのも良いでしょう。
専門機関の人々は、対話のプロ。
話を聞いてもらうだけでも、きっとなんとなく自分を受け入れてもらえたような気持ちになれるはずです。
対話をすることで自己理解も深まり、だんだんと気持ちが楽になっていくことでしょう。
 カウンセラー
カウンセラー私たちにぜひ、相談をしてみてください◎
人間関係のお悩みも一緒に解決していきましょう。
自分自身の気持ちの変化を客観視し、自己理解を深める
アダルトチルドレンの克服には、自分と向き合い、理解してあげることが最も重要です。
今まで自分が抱えてきた感情と向き合い、「どうしてそう思ったんだろう?」と考えてみてください。
そうすることで「そうか、自分はこれが悲しかったんだ」と理解し、本来の自分を認めてあげることにつながります。
傷ついた心を少しずつ認め自己理解を進めることで、自己否定感を緩和していくことができるはずです。
アダルトチルドレンを知り、自分を癒す旅に出かけよう


様々なタイプに分類されるものの、どのタイプでも自己否定感や責任感から逃れられずに苦しんでいることが多いアダルトチルドレン。
しかしその苦しみや生きづらさは、あなたのせいではありません。
さらに、自分がアダルトチルドレンであると自覚して、自分を認め、理解してあげることで、その苦しさから脱却することだってできるのです。
あなたは現在、生きづらさを感じてしまっていないでしょうか。
ひとりで悩まず、苦しまず、まずは専門機関や周りの信頼できる人に相談してみてくださいね。
具体的にアダルトチルドレンを克服する方法については、「アダルトチルドレンは解消できる?自己理解やカウンセリングの必要性とは」で紹介をしています。